
読みやすい文章の書き方:スマホ読者が喜ぶ「見た目&リズム」編
目次
文章を書いてみるけれどーー
◆読みづらくないか心配になる
◆「読みづらい」と言われる
ので、どうにか「読みやすい文章」を書けるようになりたい。
けれども「読みやすい文章の書き方」が分からない。
そうお悩みの方が多いようです。
読みやすい文章の書き方のポイントは色々ありますが、主にーー
1.見た目&リズム
2.言葉の選択
3.全体の構成
の3つを押さえておくと「読みづらい」から卒業しやすくなります。
当記事では、この3つのうちの1つ目、文章の「見た目&リズム」にフォーカスした「読みやすい文章の書き方」を紹介していきます。
2つ目の「言葉の選択」については、公開中の記事
『読みやすい文章の書き方:読者に優しい「言葉の選択」編』
をご覧ください。
ご参考になりましたら幸いです。
3つ目の「全体の構成」については、2025年7月末にUP予定です。
もしよろしければ当ブログのチェックをぜひよろしくお願いします。
前知識:Web文章が読みづらい原因

早速、読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」編を…といきたいところなのですが、
まずは「なぜ読みづらい文章になってしまうのか?」その原因を紹介します。
単にノウハウだけを覚えるだけよりも「読みやすい文章の書き方」を意識しやすくなるからです。
「原因なんていいから早く読みやすい文章の書き方を教えて!」という方は、目次から「本編」をクリックしてください。
1.見た目&リズム
Web文章が読みづらい原因の1つ目はーー
◆文章の見た目が混雑している
◆音読したときにリズムが悪くつっかえる
など「見た目&リズム」が良くないことです。
これらはーー
◇句読点
◇改行
◇行間開け
◇「」の利用
◇漢字・カタカナ・ひらがなの選択
◇「ふりがな」をつける
などで解消できます。
2.言葉の選択
Web文章が読みづらい原因の2つ目はーー
◆日本語英語の乱用
◆解説なしの専門用語の使用
など「言葉の選択」が良くないことです。
言葉選びはもちろんーー
◇どのような界隈(かいわい)
◇どの年代
に向けて書くのかにもよってきます。
しかし、どのような界隈でも年代でも、知識や流行の取り入れには「個人差」があります。
「これくらい知っているだろう」や「知っていて当然」といったお気持ちは禁物です。
3.全体の構成
Web文章が読みづらい原因の3つ目はーー
◆本題に入るまでの前置きが長い
◆「理論や解説」が中心で「結論や具体的な実践法」が後回し
など「全体の構成」が良くないことです。
これらは、読んでいる途中で離脱される(読むのをやめられる)可能性が高くなります。
せっかく書いた文章。
最後まで読んでもらうにはーー
◆「前置き」は「最後」に回す
◆「結論や」は先に「理論や解説」は後にする
◆「具体的な実践法」を「結論」のすぐ後にいれる
◆ブログなど1つの記事にする場合は「文章の型」を使う
などが有効です。
本編:読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」編

では、いよいよ本編。
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」編を紹介していきます。
読みやすい文章は「全体の見た目」と「読むときのリズム」が圧倒的に良いもの。
そのような「全体の見た目」と「読むときのリズム」が良い文章を書くにはーー
1.「句読点」の入れ方
2.「改行」のタイミング
3.「行間開け」の活用
4.『「 」(カギカッコ)』の利用
5.「漢字・カタカナ・ひらがな」の選択
6.「ふりがな」をつける
の5つが有効です。
では1つ1つ解説していきます。
1.「句読点」の入れ方
句読点は、日本語本来の「正しい打ち方」を学びなおすのが1番ですが、文章を書く前に時間を要してしまいます。
そこで、手っ取り早く、見た目もリズムも読みやすい文章にするため、2つのコツをおさえてください。
a)無意識に息継ぎしたところ
コツの1つ目は、1回作成した文章を声に出して読みます。
そして「無意識に息継ぎしたところ、一拍いれたところ」で「、(読点)」をいれます。
b)読点3つ以上なら「2文」にする
コツ2つ目は、作成した1文に「、」が3つ以上ついている場合、文章をぶった切り「。(句点)」で締める。
こうして、思い切って1文を2文に分けるとかなり読みやすくなります。
2.「改行」のタイミング
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の2つ目は「改行」のタイミングです。
「改行」のコツを2点見ていきましょう。
a)句読点で改行
改行のコツ1つ目は「句読点」です。
文章を画面が縦長なスマートフォンで閲覧する場合「。(句点)」で改行してあると、文字を目で追うとき、圧倒的に読みやすくなります。
また、1文が長めのときは「、(読点)」でも改行してあると、読みやすさがUPします。
ちなみに最近のSNS界隈(かいわい)、というより若い世代では「。(句点)」が敬遠されがちとのこと。
改行をうまく使って句読点を使わないのもありです。
ただ、ブログなど「記事」にする場合は、句読点は必要です。
句読点は打ちつつ、改行をうまく利用して、見やすく読みやすい文章を目指してみてください。
b)単語の羅列で改行
改行のコツ2つ目は「単語の羅列(られつ)」です。
例えばーー
「文章は、句読点や改行や行間開けなどを活用することで、読みやすくなります。」
という文章でしたら
句読点・改行・行間開けといった単語の羅列を以下のように
「文章は『句読点・改行・行間開け』などを活用することで、読みやすくなります。」
とするのも、読みやすい文章のテクニックです。
しかし、スマートフォンで閲覧されやすいWeb文章の場合は「単語ごとに改行する」ことで、以下のようにさらに読みやすくすることができます。
ー・ー・ー・ー
例)
文章はーー
◆句読点
◆改行
◆行間開け
などを活用することで、読みやすくなります。
ー・ー・ー・ー
このコツは、単語の羅列だけでなく、いくつかの例を出すときなどにも有効です。
3.「行間開け」の活用
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の3つ目は「行間開け」の活用です。
Web記事やSNS投稿など、文章全体を見たときに、文字が「詰まっている文章」よりも「行間がある文章」の方が、断然読みやすいです。
程よく行間を取り入れることで「読まずに飛ばされる」ことが少なくなります。
行間を活用するタイミングは、主に3つ。
さらりと解説していきます。
a)句点で改行
まず、フォント(文字)の大きさが11か12で、1文が2〜3行になる場合は「。(句点)」で改行。
さらに、もう1度改行して、次の1分との行間を1行開けると、スマートフォンでもパソコンでも、閲覧したときに読みやすくなります。
b)2〜3行ごと
1文が短く、1行で終わることが多くても「2行書いたら1行開ける」をすると、読みやすいです。
c)話の変わり目
上記のaやbの「行間開け」がふさわしくない文章のときでもーー
◆話の変わり目
◆接続詞
などで1行あけると、読みやすいです。
以上「行間明けの活用法」を3つ紹介しました。
ぜひ活用していただけると、読み手が助かります。
〜 おまけの内緒話 〜
この「行間開け」は、老眼が始まり「どこの行を読んでいたか、分からなくなる」といった、40代50代以上の「黙読迷子」世代を救ってくれます。
4.『「 」(カギカッコ)』の利用
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の4つ目は『「 」(カギカッコ)』の利用です。
例文とともに3つのり用法を紹介します。
A.人の気持ちを表す言葉
例)「どこの行を読んでいたか、分からなくなった」といいた方には〜
B.大切な言葉・強調したい言葉
例)この「行間開け」は、スマホユーザーに親切なテクニックです。
例)1文が短く、1行で終わることが多くても「2行書いたら1行開ける」をすると、読みやすいです。
C.書き手の造語
例)40代50代以上の「黙読迷子」世代を救ってくれます。
以上、上記A〜Cのようなときに、「 」を利用してみてください。
例えばーー
◆読みやすい文章の書き方、見た目&リズムの3つ目は、行間開けの活用です。
よりも
◆読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の3つ目は「行間開け」の活用です。
の方が、文章の見た目も良く、読むときのリズムもスムーズになり、読み手の理解度がUPします。
5.「漢字・カタカナ・ひらがな」の選択
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の5つ目は「漢字・カタカナ・ひらがな」の選択です。
a)ひらがな>カタカナ>漢字
日本語は、一般的に習う順の方が、読みやすいといわれています。
例えば、野菜の人参ならーー
・「人参」よりも
・「ニンジン」のほうが読みやすく
・「にんじん」のほうが、さらに読みやすい
とされています。
しかしこれは、個人差があったり、文章の内容によったりなので、必ずというわけではありません。
どの表記にするか迷ったときに「ひらがな>カタカナ>漢字」を意識してみてください。
b)同記事内では同表記を使う
同記事内では、同じ単語は同じ表記を使わないと見づらい文章になってしまいます。
例えば1箇所ーー
◆「にんじん」としたなら、出てくる「にんじん」全てをひらがなに
◆「ニンジン」とカタカナ表記にしたなら、全ての「ニンジン」をカタカナに
◆「人参」と漢字表記にしたなら、全ての「人参」を漢字に
と、揃えてください。
C)同表記をくっつけない
ちなみに、上記「a」で「ひらがな>カタカナ>漢字」について触れました。
しかし、名詞をひらがなにすると、助詞(てにをは)のひらがなとくっついてしまい、読みづらい場合があります。
例えばーー
◆にんじんを入れます
◆にんじんが好きです
などよりも
◆ニンジンを入れます
◆人参が好きです
などのほうが読みやすいと思います
もちろん「ひらがな」だけでなく「カタカナとカタカナ」そして「漢字と漢字」がくっついているのも読みづらいことは、皆様もご経験済みではないでしょうか?
細かいことだと感じるかもしれません。
しかし「ひらがな・カタカナ・漢字」の「どの表記」を選択するのか?
そして、同じ表記がくっついた文章になってしまう場合ーー
◆「、(読点)」
◆「・(中黒)」
◆「 」
◆改行
などをどう使うのか?
いつでも、読み手の立場に立って「細かい心遣い」をすることが、読みやすい文章を書く最大のコツではないかと思います。
5.「ふりがな」をつける
読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」の5つ目は「ふりがな」をつけるです。
ご自身が読める漢字でも、読み手全員が読めるとは限りません。
読めない漢字があると、読み手は「読み方」を調べないといけなくなり、読み続けるのが面倒になってしまいます。
とはいえ、どの漢字が読めて、どの漢字が読めないのか?
それは、読み手によるので、どの漢字にふりがなを打てばよいか分からないですよね。
あくまで目安なのですがーー
◆日常生活で出てこない漢字
◆話の流れからも予測できない漢字
◆過去にご自身が読めなかった漢字
には、ふりがなを打つとスムーズです。
ちなみに「ふりがな」は、パソコンの機能で「漢字の上にルビを打つ」方法があります。
しかし、パソコンと言うより、使用しているサイトの仕様で「ルビが打てない」場合も多々あります。
そんなときは、漢字の後ろに「半角カッコ( )」で囲って「ふりがな」を打つと分かりやすいです。
あとがき:スマホ読者を喜ばせよう!

ここまで「読みやすい文章の書き方」をーー
1.「句読点」の入れ方
2.「改行」のタイミング
3.「行間開け」の活用
4.『「 」(カギカッコ)』の利用
5.「漢字・カタカナ・ひらがな」の選択
6.「ふりがな」をつける
など、文章の「見た目&リズム」にフォーカスして紹介してきました。
近年、文章は「ブログ・SNS・Webメディア・オウンドメディア」などーー
◆書き手は「文章をWeb上に投稿する」
◆読み手は「文章をスマートフォンで閲覧する(読む)」
ことが、圧倒的に多いです。
この「文章をスマートフォンで閲覧する(読む)」読み手を、ここでは「スマホ読者」と呼ばせていただきます。
そして、本編でも触れましたが、スマートフォンの画面は縦長がほとんどです。
今回、当記事の『読みやすい文章の書き方「見た目&リズム」編』の5つはーー
◆内容を理解しやすい見た目
◆縦長画面用にスイスイ読めるリズム
で、スマホ読者の「脳」と「目」を喜ばせてくれるテクニックとなっています。
皆様が、読みやすい文章を提供し、たくさんのスマホ読者さんを喜ばせてくださることを心より願っております。
当記事がお役に立てましたら幸いです。
「読みやすい文章を書きたい」
「読みやすいブログ記事を書きたい」
「読みやすいWeb記事を書きたい」
「エッセイストになりたい」
だけど…
・読みやすい文章の書き方が分からない
・ブログ記事やWeb記事の書き方が分からない
・エッセイストになる方法が分からない
という皆様に向けた
ライティングスクールがあります!
18ステップのカリキュラムに
潮凪洋介塾長をと現役エッセイスト7名が講師を努め
全くの文章初心者の生徒さんが
6ヶ月後の卒業時には
「WEBメディア」のオーディションに受かり
連載を勝ち取る「エッセイスト」へと成長しています。
カリキュラムでは課題提出があり
実際の文章の添削指導も充実。
ご自身の分野で文章を書いて発信し
何歳からでもエッセイストになれる
『オンラインライディングスクール「WRITAS!(ライタス)」』
のカリキュラム内容やシステムの詳細はこちらから
講師・スタッフ一同
Webライティングをしたい方をお待ちしております!
『オンラインライティングスクール「WRITAS!」』by潮凪道場
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
当記事の他にもエッセイスト養成塾
「潮凪(しおなぎ)道場ブログ」にて
「文章のコツ・テーマの選び方」などを掲載しております。
宜しければぜひ覗いてみてください。
文章を書きたい皆様のお役に立てましたら幸いです。
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
■記事
オンラインライティングスクール
「WRITAS!(ライタス)」
ステップ10・11担当講師:かがみやえこ
■画像
写真AC
最後までお読みいただきありがとうございました。




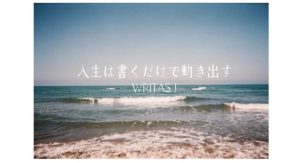
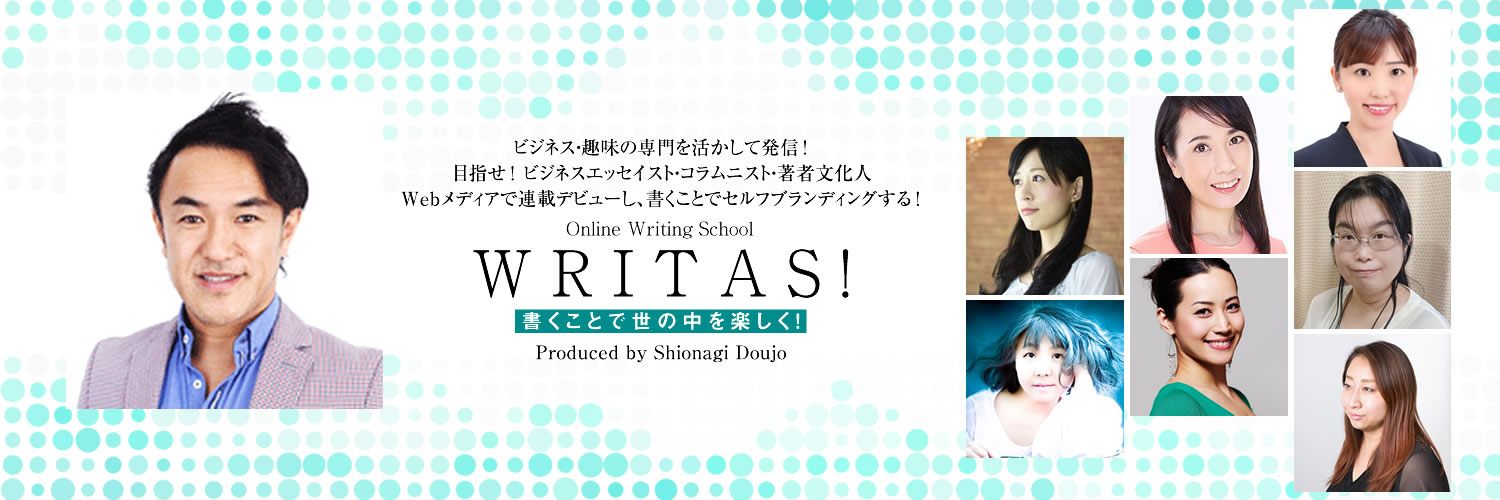







この記事へのコメントはありません。